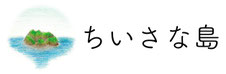公衆電話はいっとき絶滅の危機に瀕したが、震災を経験したことで固定ライフラインの重要性が高まりかろうじて生き残った。二十年前ではごく当たり前にあった公衆電話であるが、あれよあれよという間に減少し、財布に定位置を締めていたテレホンカードが姿を完全に消して以来使った記憶がない。妻がテレカと言ったときに瞬時にテレホンカードの略であることを認識できずに、心の中で「え」と言ってしまった。声にだして「え」と言わないあたりにぼくの奥ゆかしさがあるのだが、声にだして「え」と言える程度にはコミュニケーション能力を高めたいと思う今日このごろである。
これは築五十年を迎えた団地の敷地内にある唯一の公衆電話である。以前は携帯電話を持たない(持てない)外国人がよく占拠して使っていたが、携帯電話のSIMフリー化にともないそうした姿すらついぞ見かけなくなった。日本人であればなおさらである。その証拠に順番を待っているひとでさえすでにその使い方が間違っているではないか!
ドリフのコントには公衆電話は定番の小道具だった。長蛇の列ができているにかかわらず無神経に電話で話し続けるひとに後ろのひとがついに怒り理不尽な揉め事が始まるというのがお決まりのパターンであるが、現代のひとにはまず公衆電話がなんたるかというところから説明をしないとわからない。しかしそれがわかったところで電話順を待つというイライラを経験したことがないからこの面白さを本当には理解できないのであろう。
かつて小室哲哉が時代が変わると意味が通じなくなる言葉はこれからは使わないようにしたいと言っていた。「ダイヤルを回す…」「受話器をとる…」「電話ボックス…」、微妙な恋心を表現するこうしたツールが今のひとには通じない。そうした時代性を感じるセリフは古いもの、時代遅れのレッテルを貼られるのがいつも時代の先端を目指していた小室哲哉は嫌だったのだろう。
“電話ボックスに忘れたカセットできみのメッセージぼくに伝わった…”
TM Network(当時はTMN)の楽曲1990年発表のThe point of lover's nightという曲は冒頭をこの言葉で始まる。当時ぼくは中学三年生だった。この曲を聞くとそのときに感じていたことが眼前にありありと思い浮かぶ。ぼくは時代性を感じる言葉は嫌いじゃあない。それが若い世代に古いと一蹴されようとそんなことは大した問題ではないからだ。
人間は外界からの情報の90%以上を視覚から得ていると言われているが、記憶と密接に結びついているのは聴覚や嗅覚だったりする。音楽はとくにその力が強く、ある曲を聞くとそれに付随して想い出が次々と蘇る。昔観た懐かしい映画を今もう一度みたからといって音楽のようなことは起こらない。これがぼくが映像や写真を生業としていてもっとも歯がゆいところなのだ。印象や記憶への紐づけの強さという点で映像や写真は音楽にまったく歯がたたない。
だからぼくの音楽への憧れというのは常にあって、子供ができたら最初に聴かせる音楽はぼくの自作の歌にすると決めていたくらいだ(音楽家と違って自分の子供くらいしか発表する相手がいないのだ)。
映像や写真と記憶への結びつきについて、音楽ほどにはならなくても少しでも強くできないか。それについて20年以上試行錯誤を続けてきたし、今も続けている。対外的にはアメリカの大学院を出たというほうが聞こえがいいらしいが、個人的には独学で得た知識やノウハウこそが膨大だ。
ところで日本ではどこそこの大学に「入った」或いは「行った」と言い方をするが、アメリカではどこそこ大学「出」という言い方をする。それは日本の大学は入試こそが最大の難関であり入ってしまえば卒業できないやつなどいないに等しい上、中退などという言葉がまかり通るのもそのせいであるが、アメリカでは入るのは比較的簡単だが、卒業するとなると本当に勉強して合格点に達しないとできないシステムだからだ。閑話休題。
公衆電話からだいぶ遠くへ行ってしまった。今ぼくの手元にあるテレホンカードはオリックス時代のイチローがバットをかまえて片足で立っている写真のが一枚ある。野球にまったく興味がないぼくなのでコレクションではなく実際に使おうと思っていてそのまま使わずになってしまっただけのことである。災害時に使うかもしれないと思いとってあるが、できれば永遠に使わずに済みたいものだ。それに最新式(?)のグレーの公衆電話はテレホンカードが使えないようである。上野でイラン人が偽造テレカを売りさばいていたのも遠い昔々の出来事だ。